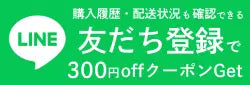萩焼
使うほどに変化する、侘び寂びの美
萩焼は、日本の陶磁器の中でも特に「侘び寂び」を象徴する焼き物のひとつです。
市を中心に生産され、茶道との関わりが深く、使い込むほどに風合いが増し「萩の七化け」と呼ばれる特徴を持っています。
萩焼の歴史は、16世紀末の「文禄・慶長の役」に遡ります。
戦国大名・毛利輝元が、朝鮮から連れ帰った陶工・李勺光(りしゃっこう)や李敬(りけい)らによって開窯されました。
朝鮮半島の陶芸技術をベースに、温かみのある柔らかな質感の焼き物を繰り返しました。 以来、萩焼は茶人たちに愛され、「一楽二萩三唐津」と呼ばれるほど茶陶として高く評価されてきました。
柔らかく温かみのある質感
萩焼は、土の粒子が粗く、吸水性が高いのが特徴です。
そのため、使い込むうちに茶や酒がしみ込み、色合いが変化していきます。この変化が「萩の七化け」と呼ばれます、長く使うほどに自分だけの器になっていきます。

0 商品
このコレクションに商品はありません